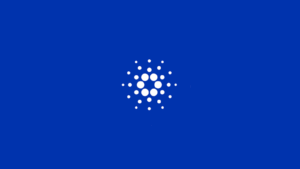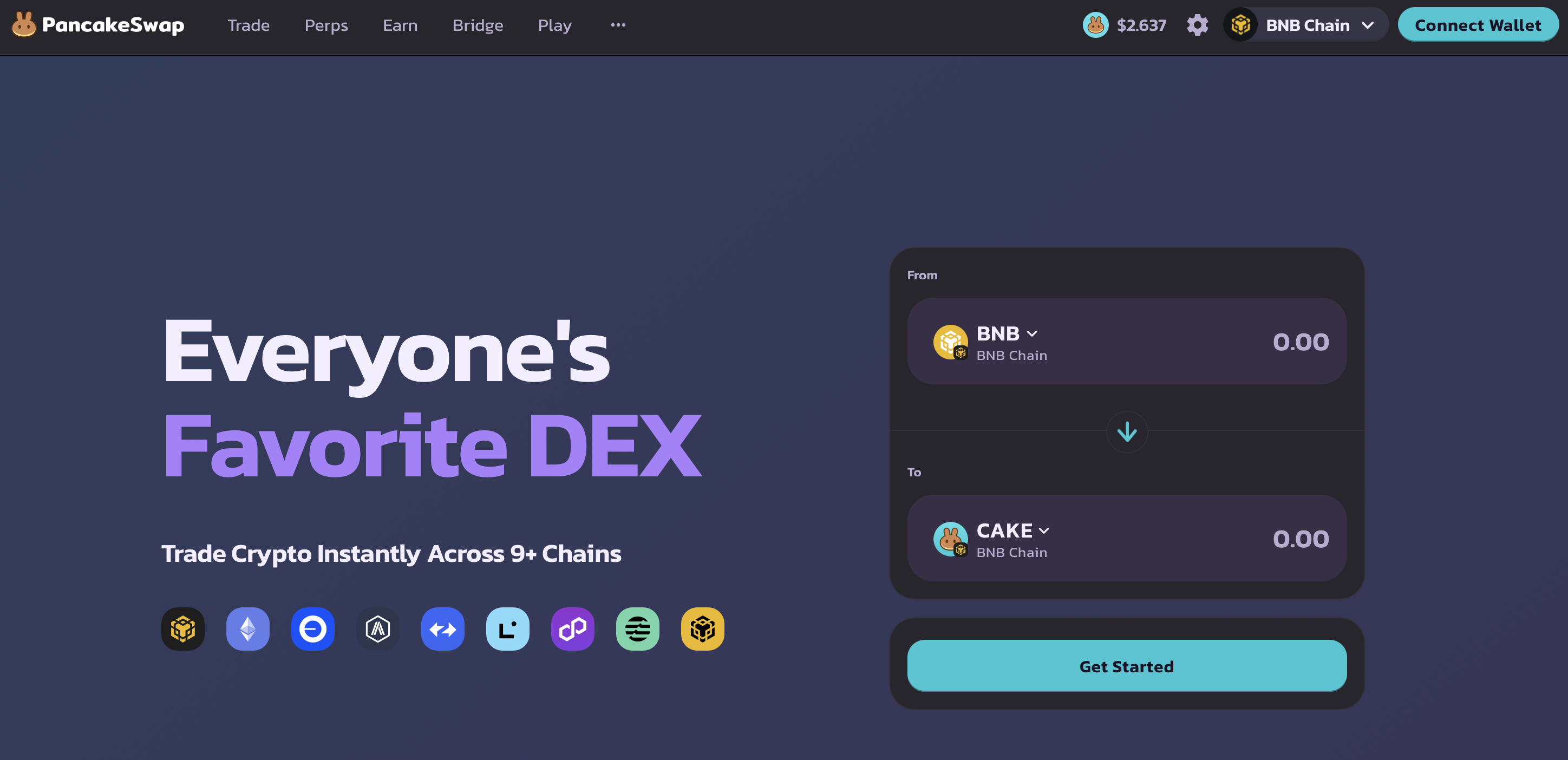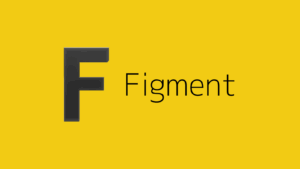はじめに
これまでこの連載では、国内CEXなどの「企業に任せる」ステーキングの仕組みを紹介してきました。
確かに、こうしたサービスは手軽で始めやすいです。私も慣れてくるまでは、CEXでの取引と運用をお勧めしています。
でも、それって本当にWeb3的なステーキングなのでしょうか?
ブロックチェーンのステーキングとは、本来自分の意思でネットワークに参加し、支える行為です。
今回は「全部自分で行う」という視点から、中央集権に頼らないWeb3的ステーキングの魅力と仕組みを解説します。
余裕がある方、これを機に、非中央集権を体験したい方はぜひ最後までお読みください。
ステーキングには「委任(Delegate)」という選択肢がある
ステーキングというと、「預けておけば利息のように報酬がもらえる仕組み」と考える方も多いかもしれません。しかしその裏では、あなたの資産がブロックチェーンの安全性や取引処理を支えるために使われているのです。
とはいえ、すべての人がノードを立てて、ブロックチェーンを直接運用するのは現実的ではありません。
例えば、Ethereumでソロステーキングを行うには、32ETH(約1180万円)を用意し、自分でノードを構築し、24時間稼働させ続ける必要があります。通信環境やセキュリティ管理も欠かせず、一般ユーザーにはかなりハードルが高い仕組みです。
そこで、多くのチェーンでは「自分で運用するのではなく、信頼する人(=バリデーター)に託す」という仕組みを採用しています。
これが、dPoS(Delegated Proof of Stake)=委任型プルーフ・オブ・ステークと呼ばれるモデルです。
この「委任できる」という構造こそが、dPoSが多くのユーザーに支持される理由でもあります。
なぜ、dPoSを採用するチェーンがあるのか?
それはブロックチェーンの安全性を保ちつつ、多くのユーザーが参加できる仕組みをつくるためです。
| dPoSを採用する目的 | 解説 |
|---|---|
| ✅ 高速な処理とスケーラビリティ | 少数のバリデーターで合意形成するため、処理速度が速くなる |
| ✅ 参加のしやすさ | ノード運用せずとも、トークンを委任するだけで参加できる |
| ✅ 健全な競争 | 委任者が「信頼できるバリデーター」を選ぶことで、透明性や競争原理が働く |
| ✅ 分散性と効率のバランス | バリデーター数を制限しつつも、委任者によって分散性が保たれる |
つまり、dPoSは「誰でもネットワークに関与できる」道を開きながら、効率性も両立した仕組みなのです。
dPoSの基本構造
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| 委任者(Delegator) | 自分のトークンを信頼するバリデーターに預けてステーク |
| バリデーター | 委任を受けてブロックを検証し、報酬を得て分配 |
| 報酬分配 | 委任者は報酬の一部を受け取り、バリデーターは手数料を得る |
この仕組みにより、ノード運用の知識がなくてもネットワークに参加できる一方で、
「誰に委任するか」というユーザーの意思が、ネットワークの健全性に直接影響を与えるのです。
dPoS採用チェーン:あなたの意思で選べるネットワークたち
dPoSを採用している代表的なブロックチェーンには、以下のようなものがあります。
- Solana:Phantomなどのウォレットからバリデーターを選んで委任可能
- Cosmos Hub:Keplrウォレットを使い、アクティブバリデーターに簡単に委任できる
- Sui:Slush Walletなどを利用して、Epochごとにバリデーターを選び、SUIを委任できる
- Avalanche:バリデーターの選定が必要な部分的なdPoS構造
- Polkadot:ノミネーターとして候補者に委任。報酬は選定されたバリデーターによって分配される
これらのチェーンでは、ウォレット内のステーキング機能から「どのノードに預けるか」を選ぶ体験が提供されます。
それは単なる利回り選びではなく、信頼、方針、セキュリティを自分で判断して選ぶというWeb3的な意思表示です。
Ethereumの場合
EthereumはdPoSを採用しておらず、SolanaやSuiのように直接委任先を選ぶ仕組みは存在しません。
ステーキングには原則32ETHが必要で、ノードを自分で立てる必要があります(ソロステーキング)。
しかし、現実には多くのユーザーがLidoやRocket Poolといったリキッドステーキングサービスを使ってEthereumに参加しています。
✅ Lidoの特徴
- ETHを預けると、stETHというトークンが発行される
- Lidoが選定した複数のバリデーターにETHが分散してステークされる
- stETHを保有しながら報酬を受け取れる(DeFi活用も可能)
- ノンカストディ型で、一定の分散性と透明性を保っている
Lidoのような仕組みは、Ethereumにおける“委任的ステーキング”の現実解といえるでしょう。
ユーザー自身がバリデーターを直接選べるわけではありませんが、中央集権CEXとは異なる分散的な運用構造を持っています。
「全部自分でやる」とは、意思をもって「選ぶ」こと
「自分で行う」というと、ノード構築や専門知識が必要に思えるかもしれません。
しかし、Web3的ステーキングにおける「自分でやる」とは、むしろ「自分の意思で委任先を選ぶ」ことに他なりません。
たとえば
| 委任先を選ばない場合 | 委任先を選ぶ場合 |
|---|---|
| 中央集権企業が自動的に配分 | 自分で調べて信頼できるバリデーターに託す |
| ガバナンス投票に間接参加できない | 投票方針を持つバリデーターを通じて意思を示せる |
| リスクや手数料がブラックボックス | 公開情報を比較して判断できる |
つまり、「委任する」とは責任のある参加であり、分散型ネットワークに貢献する意思表示でもあるのです。
おわりに:ステーキングはWeb3への参加表明
これまでのように、CEXや企業に「預ける」だけでもステーキングはできます。
でも、Web3的な視点で見れば、それだけでは自分の力でネットワークを動かしている実感は得られません。
「全部自分でやる」というのは、ノードを建てることではなく、自分で調べ、自分で選び、自分で委任すること。
それが、これからのWeb3ユーザーに求められる姿勢なのではないでしょうか。
難易度は高いですが、メリットはあります。CEXに取られる手数料がないため、自分でやった方が利回りが高くなります。リスク管理など、学ぶことは多くなってしまいます。ですので、責任転嫁タイプの人はやめておいた方がいいですね。しかし、そうじゃないなら、試してみる価値はありです。ただしこれだけは忘れずに、
DYOR!!